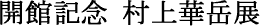
|
 太子樹下禅那之図 1938年 |
 巒峯茂松 1939年 |
|
太子樹下禅那 梶川芳友 |
|
誰にも生涯を決定するふしぎな邂逅というものがある。
昭和38年秋、自分の進路に悩んでいた22歳の私は、近代美術館京都分館の「村上華岳の芸術」展に何気なく入った。そこで出会った「太子樹下禅那」の強烈な印象を忘れることは出来ない。 それは絵の巧さ、美しさという次元ではなく、この世の中にこんな人間がいたのか、という驚きであった。私はこれまで体験したことのない、身ぶるいするほどの感動を受けた。「閉館ですよ」と係員に声をかけられるまでその場に立ち尽くしていたのである。 私はこの作品によって、生涯を美術のことにかけようと決意した。と同時に、この画はきっと自分の元に来るという妙な予感が心に浮かんだ。 そして私の華岳を求める巡礼の旅が始まった。 華岳の有無をいわせない力に動かされ “華岳の信者”と呼ばれる全国のコレクターたちを訪ね歩いた。その旅に秘めた思いを受け止めるかのように、生と死、肉体と精神、その矛盾した裏側の深みを凝視する画家の眼が、私を射るのである。 17年後の昭和55年2月、予感は現実となった。私は神戸六甲の山々に見送られ「太子樹下禅那」をだきかかえるようにして、京都へ帰ったのである。 晩年の華岳は、毎夜起こる喘息の発作と、それを抑える劇薬の服用で、肉体的苦痛の極限にあった。しかし彼は、衰えてゆく身を切り刻み、常に相反するものを同居させ、筆を執りつづけていたのである。 尼連禅河畔、菩提樹下で坐禅修行する若き日の悉多太子の画には、苦しみなど微塵も感じさせない。この作品は今も、生きるための重大な問題を問いかけてくれ、あらゆる私の考え方の出発点になっている。 華岳の強靭な精神力は、既成の絵画の枠組みを超えて常に自由であった。その魂は「何ぞ、必ずしも」と常に定説を疑い、自由な精神を持ちつづけたいという私の願いに通じている。何必館・京都現代美術館は、村上華岳のための美術館といっても過言ではない。 7年の歳月を要した美術館の5階には、特別展示室を設け「太子樹下禅那」を掛ける最上の空間となるよう設計した。そして開館記念展は、全館を80点の華岳作品で埋めた。それが生涯に確かな方向を与えてくれた華岳への、私の精一杯の表現であった。 「製作は密室の祈りなり」という華岳の言葉には、芸術の深遠をかいま見た、恐ろしさときびしさを感じる。 作品は人間の戸籍であり、心の遺言である。そこに人間の血に宿る歴史の深層をみるとき、ひとは人生の確かな道筋を発見するのかもしれない。 |
| 年譜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
関連グッズ
→ミュージアムグッズ一覧はこちらへ  
|